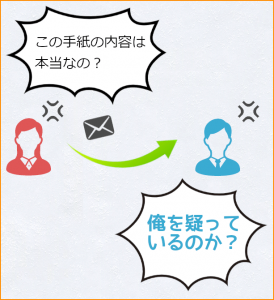初回の密告電話のパターンは2通り。それぞれの使い分けを説明します。
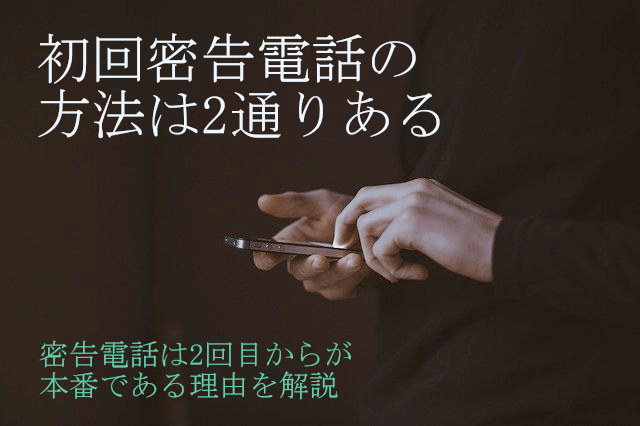
久しぶりの更新となります。
なお、私としてはあまり記事を公開したくありません。
なぜかというと、泥棒が防犯の書籍を参考にするように、
密告する側にとっても有益な情報を与えてしまっているためです。
事実、当ブログを参考に密告された方の報告もいただいております。
ただ、密告に関する情報はあまり表にでてきません。
表にでてきても、あまり内情に詳しくない方が脚色を加えて
自己流に書いた、二次・三次情報がほとんどです。
そこで、訂正の意味合いも込めて当ブログを運営しています。
できるかぎり、公開する情報は深堀りはせず、悪用をしてもどこかで
つまづくようにしています。その点を考慮してお読みいただきたく願います。
密告に悩まされている方は当ブログの情報だけを参考にせず、
相談員の私(六条)にご連絡ください。
2020年5月23日 記
目次
■密告電話の初回メッセージの伝え方は2通りある
密告電話は基本非通知でおこないます。
こちら側(密告側)の情報はできるだけ与えないメリットがあるからです。
ですが、デメリットもあります。それは、警戒心を当初から与えてしまうこと。
そのため、最初の関門は相手が電話にでてくれるかどうか。
この関門を抜けなければならないのですね。
たとえ非通知でなくとも、相手の登録リストに入っていない電話番号でかけることになります。
どうしても突破すべき関門があるのです。
しかし、この関門は相手の判断によってゆだねられています。
「電話にでる」「電話にでない」この主導権は相手にあります。
では、その関門を抜けたあとはどうするのか? ここで選択肢がわかれます。
なにせ、相手は非通知という電話にでたものの、警戒心を抱いているわけですから。
非通知とは登録リストに居ない人物、見も知らない人物からの電話とおもって当然です。
そこで、密告業者は相手が警戒心ているものとわかったうえで 2通りの方法をつかいわけます。
- 最初から本題に入るパターン
- 警戒心をできるだけ低めてから本題に入るパターン
1は、相手が電話にでた瞬間から伝えたい重要なメッセージを伝える方法です。
開口一番に自分の伝えたいメッセージをズバッと言い放ちます。
たとえば不倫に関する密告であれば以下の台詞が該当します。
不正の密告であれば「〇〇課の鈴木太郎は不正を働いています」などのメッセージに
なるでしょう。
この方法はすでに相手(被密告者)が配偶者の不倫に感づいているとき。
または被密告者の性格上、長話ができないと判断したときに採用されます。
2は、じっくり話を聞いて欲しいときに採用される方法です。
または、相手が性格上、話を聞くタイプであると最初からわかっているときに使われます。
「お世話になっております、〇〇でお会いした鈴木花子です~」と、
すでに被密告者の知見を得ていると誤認させるように話を切り出すのが一般的な手法です。
腕の良い密告業者だと電話の切りだし方をいくつももっており、状況によって使い分けます。
これは「なりすまし」と呼ばれる電話工作のひとつです。
ただ、被密告者の友人や知人の実名を使用するとばれる可能性があるので多用はしません。
「なりすまし」にも実在の人物を利用する方法と、架空の人物をつくりだす方法があるのですね。
なお、後者は厳密には「なりすまし」とは呼べないのでご注意ください。
ただ、一般的に架空の人物をつくりあげて役割を持たせるのも「なりすまし」と呼ばれています。
初回メッセージの使い分けを説明
すこし掘り下げてみましょう。
1の手法が採用される主なケースは以下となります。
- どうしても伝えたい事柄がある
- 伝える量が少ない
- 相手(被密告者)が、密告したい件についてある程度の知識を持っている
- 数回電話をかけたあと
最優先でこれだけは伝えたい事柄がある場合には、1の方法(最重要情報を開口一番に伝える方法)
が採用されがちです。なぜなら、通常の密告電話は相手が聞く姿勢ではないためです。
いきなり非通知や知らない番号がから電話が掛かってくるのです
警戒心をもっていて当然ですよね。だからこそ、ひと言目から伝えたい事柄を話します。
さらに、密告者が最優先する事柄というのは、相手の興味を引く内容であるケースが
ほとんどです。そのため、最初に興味を引く事柄を伝えて、その先の会話を成立させる
土台をつくりだせるという利点もあります。
たとえば夫が不倫をしていると考えもしない既婚女性(妻のAさん)に密告電話をかけるとします。
初回の電話であいさつもせずに、いきなり「あなたの夫が不倫をしています」と伝えます。
すると「え? 夫が…それは本当ですか? それよりあなたは誰ですか?」と、
会話がつながっていくのですね。
また、Aさんが夫の不倫にうすうす感づいていたときには、
「やはりそうですか。ところであなたは誰なのですか?その証拠はあるのでしょうか?」
と、やはり話はつながっていきます。
ただし、あくまでもうまくいったときの例です。
悪戯とおもわれてすぐ切られてしまうデメリットもあるのですから。
現実的に、この1の方法がとられるのは数回電話をかけて無視をされたあと、
相手が「電話主はいったい誰なんだろう?」と、しぶしぶ電話にでたときです。
相手の立場になって考えるとわかります。
相手は非通知で誰かもわからない相手の電話を無視しつづけてきたのです。
でも、多少の好奇心と不快感から電話にでてしまったのですね。
誰かの電話番号と間違えているかもしれないのであれば、間違いを教えてあげる。
悪戯であれば、怒鳴りつけるなど、どのような行動をとるかを思案しているでしょう。
そこで、ようやく電話を受け取ったのです。
この場合、ほとんどの方は警戒心を抱いているので無言です。
相手=密告者の様子をうかがうためですね。
言い換えれば、密告者のひと言を待っているわけです。
そうです。
電話の受け取り側としては「息をひそめて密告者の開口一番の言葉を待っている」のです。
密告者の立場からすれば、これから発するひと言で密告が成功するかどうかがわかれます。
この時点で、2の方法を採用しても、相手の記憶力がよかったり、勘が鋭い方であれば
すぐに見抜かれます。嘘がばれると相手(被密告者)からの信用を得られません。
そのため、開口一番に重要な内容、相手にとって衝撃的な情報を伝えるのですね。
たったひと言を伝えたあとに電話を切られても、最重要項目(情報)は
相手に与えられたわけですから。
そして、これはあとあとの布石にもなりえます。
被密告者は密告電話をいちど受けたのです。
ほぼ疑念が抱くのですね。そしてその情報が本当かどうか気になる。
そして、追加情報を求めるために、密告電話を待つ体勢になっていきます。
そうなれば密告者はしめたもの。あとは悠々と電話口で言いたいこと言うだけです。
2が採用されるケース
2が採用されるケースは以下。
・相手の性格上、電話をすぐに切られるとおもわれるとき
・相手が話を聞く姿勢を見せているとき ※初回の密告電話が成功していた場合
密告をしたい方(依頼者)から相談をうけるとき、密告をする相手の情報ももらいます。
そのときに、性格の話をされるのも珍しくありませんでした。
(例)「あの奥さまはちょっときつい性格なので、あやしまれるとすぐに電話を切られるとおもいます」
そのため、相手の性格によっては警戒心を解くのを優先していました。
1のようにメッセージ優先とはしません。
まずは「私は敵ではない。味方です」と意思表示をするのですね。
次に、2の方法が採用されるケースとしては「すでに密告電話が成功していた場合」です。
相手がからすれば、以前の「密告者がまた密告電話をかけてきたという」状況になります。
初回の密告電話では、自身の身分についての説明は皆無。
2回目で自身(密告者)の情報を開示する。
段階的に開示する方法ですね。
1回、密告電話受けた経験がある人物のその後の対応は2通り。
ひとつは無視。最初から電話にでないのですね。
もうひとつは「とりあえす聞く」こと。
警戒心は持ってはいるが、相手(密告者)の言動が気になっている状態です。
「自身で密告者の情報を精査してみると事実であった」というときには
貴重な情報源として、密告者の話を聞くでしょう。
そのため、性急になんの脈絡もなく伝えたい事柄を一方的に話すと、
相手は頭の整理ができません。
密告者からすれば、いわば疑いながらも受けいられている状態なので、焦る必要がないのですね。
なので、こちらの身分に関する情報を特定されない範囲で開示して、
警戒心を解くのを優先します。もし、ここで敵とみなされてしまったら
密告の件を相手方で共有されてしまうおそれがあります。
「夫Aが不倫をしていた」という密告の件が、当事者である夫Aに伝わってしまうかもしれません。
誤解を与えないためにも、まずは警戒心を下げるのを優先したのが1の方法とも言えます。
密告電話2回目の危険性とは?
初回の密告電話が成功したとしても、2回目も成功するとは限りません。
なぜなら、密告者に文句が言いたいがために、2回目の電話にでる可能性もあるからです。
または密告者の身元をさぐるために、情報を聞き出そうとしているか。
もし、あなたが密告電話をすでに1回受けた立場であれば、
2回目の密告電話を相手の情報を聞き出す好機としても活用できるのですね。
密告する側としても、2回目の電話というのは分岐点となりえます。
相手はすでに密告の電話を経験しているためです。
そしてあなたは密告された内容についても気持ちの整理がついているので、
前回よりも動揺しないでしょう。
密告者がおもわぬ反撃を受けるのは2回目からですから。
初回で事態を受け入れ、冷静になれる人は珍しいためですね。
よって、探りあいになるのは2回目からとおおもいください。
■まとめ
密告側は冒頭・序盤にズバッと重要な内容を伝えるのが基本となります。
挨拶も脈絡もなしで伝えたいことをいきなり被密告者に伝えるのですね。
電話による密告の主導権は相手にありますから、できるだけ
会話がながびかせたくはありません。
なぜなら、ボロがでてしまうおそれがあるからです。
なれていない人物が密告電話をすると、相手になにかしらのヒントを与える
危険性があるのですね。密告業者に依頼せずに、ひとりで密告電話をする人は
どこかで相手側にヒントを与えてしまっている可能性が高いというわけです。
断片的に情報を与える、または情報源としての立ち位置を確保したいのであれば
2を選択してもいいでしょう。1はメッセージ優先。単発的なイメージと捉えてください。
なんの脈絡もなく、密告したいその核をいきなりぶるけるイメージです。
もし、私怨による復讐や、悪戯でないのであればできるかぎり
密告者は自身の情報をできる範囲で開示するはずです。
一方的に事実を叩きつけるように伝える密告電話であったら、
相当相手は憤っているか、私怨が入っている可能性が高いですね。
密告者はできるかぎり自分の情報を相手に伝えたがります。
聞き入れてもらえないとなんの手立てもありません。
無駄に敵意をもたれても損をするだけです。
ただ、当記事だけを参考に密告者の立ち位置を推測するのは
危険ですのおやめください。密告者はあなたの予想以上に、
あなたの大切な人の情報を持っているのですから。